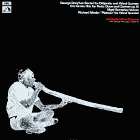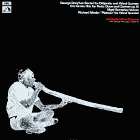現代音楽の中に西部アーネム・ランドのアボリジナルのディジュリドゥ奏者を入れて演奏するという初の試みを収録した記録的価値の高い作品。前衛的なアプローチで挑んだ意欲作。
■ライナーの翻訳
■曲解説
■GOULBURN島の録音を含む音源
このレコードに収録されている曲は全て作曲家が曲を書き、その楽譜に従ってそれぞれの楽器が演奏されている。その際にディジュリドゥ奏者George Winungujにどういった指事がされていたかは不明だが、Georgeが楽譜を読めなかった確立は高いだろう。おそらく、演奏のスタートと止めるタイミングだけが指事されているようで、生真面目に前衛的なアプローチに挑む4人の管楽器奏者をよそに、Georgeは伝統的な「Lidaro-/Ditamor」といったマウスサウンドで自分のスタイルを変える事なくのびのびとと演奏している。
内容としては非常に現代音楽的で実験的。ディジュリドゥは曲の頭と曲間にほんの短いソロがあり、そのパート以外は4つの管楽器にうもれて聞き取りにくいのが残念だ。しかし、アボリジナルの伝統楽器ディジュリドゥが、アボリジナルの演奏者によって西洋音楽の中で演奏されるという初の試みがなされたという歴史的価値の高い音源と言える。
また、アーネム・ランド北西部の「Goulburn島」のディジュリドゥ奏者が、パフォーマンスのためとはいえ、伝統曲の中では決して使われる事のないトゥーツ(ホーン/オーバートーン)やコールを巧みに操りながら、まるで現代のイダキ・マスターDjalu'
Gurruwiwiのようなパワフルな演奏を披露していて驚かされる。
ライナーには、当時の白人の側から分析したディジュリドゥの構造、演奏方法なども紹介されていて興味深い。
■ライナーの翻訳
George Dreyfus : Sextet for Didjeridu and Wind Instruments
ヨーロッパの国々の民族音楽とはちがって、オーストラリアのアボリジナルの音楽はメロディー形式やフレーズの構造、拍節的あるいは韻律的な音楽構成において、一般的にオーストラリアに共に住む白人の音楽と共有するような特徴が全くない。このレコードに収録されている音楽では、BartokやKodalyといった音楽家が行って来た、音楽の創造的な移植はなされていない。これまでオーストラリア国内におけるアボリジナルと白人の文化的交雑の試みがなされてきた。その試みがアボリジナル音楽そのものよりも、むしろアボリジナルの伝承や伝説の「詩的な面」に接点を見いだしながら、標題音楽的な詩の形式をとってきたとい事は驚くに足りない。しかしユニークな事にDreyfusの六重奏団にはアボリジナルの楽器と西洋楽器を合わせることによって、音楽的制約と音色が加わっている。またアボリジナルの楽器が伝統の中でどう機能するのかという事を描き出している。
ディジュリドゥは、白蟻が食べて中に空洞ができた木の枝で作られる。その長さ(一般的に120〜150cm)、内部の空洞の直径、木の厚みがその基本音を決定付ける。この基本音はルーズに振るわせた唇で息を吹きこんで鳴らす。唇をぴんと張った状態にすると、空気が通る隙間が狭くなって風圧が増加する。それによって基本音よりも10度上のオーバートーンが生まれる。ディジュリドゥで自由に演奏することができる音程は、このオーバートーンと基本音の二つだけである。しかし、唇が接しているディジュリドゥのマウスピースに向かって舌が近づいたり、離れたりすることで、基本音の音色を変化させることができる。演奏は自由だが、口腔内から空気を吐き出す時に行われる頬の動きによって、強調されたリズムが基本音に加わる。声を使った和音がガーガーという特別な音色を作るために使われ、それによってディジュリドゥの演奏にゴロゴロとした音質をえることができる。
ディジュリドゥはメロディー楽器というよりは、一定の音程のドローン(持続低音)を鳴らすリズム楽器である。そのドローン音はさまざまなリズムと音質に変化させることができる。長くひきのばした基本音(ドローン)は、非常にユニークな呼吸法で維持される。管の中に空気を吐き出すのに十分なだけの空気を両頬にため、音を出し続けている間に鼻からスッと短い息を吸い込む。
George Winungujはこの六重奏のためにGoulburn島からやってきたディジュリドゥのエキスパートだ。長年に渡る厳しい修行により、長時間演奏するだけの肺のパワーがある。Georgeはかなり有名なミュージシャンであり、一族の長老であり、メソジスト教会の平司祭でもある。
アボリジナルの楽器と西洋楽器を合わせようとした時、作曲家George Dreyfusは特殊な問題に直面せざるおえなかった。一方では、高度に発達した製品技術、複雑な精密機器、形式的な編成と音楽発展の洗練されたコンセプトによって作られた製品である西洋楽器があり。もう一方で、ほぼ自然の産物であるアボリジナルの楽器、楽譜を読まない演奏者、そして唄と踊りと分つ事のできない彼等の音楽があるのだ。ディジュリドゥはソロ楽器として使われることは決してない。それはディジュリドゥ単体での独立したインスト曲というのがアボリジナルの伝統にないからだ。この二つの異なる音楽を一つにし、互いのスタイルを模倣することなく、互いを合わせ共存し、しかも理路整然としているという、なにか互いに共通するポイントを見いだすということは新たなるチャレンジだ。
作曲家Dreyfusは、この管楽器のための楽曲を作るにあたって、半音階主義の時代のものにその可能性を見いだした。和音的進行や伝統的なリズムの骨格にとらわれることなく、音程の塊の斬新な変貌をへて、半音階的に展開された反響の織物を作り上げたのだ。和音の構成が重なり合「、しだいに古い形をぼやけさせ、新しいものを指し示すことによって 発展していく。音の組み合わせは、部分部分を複雑に編み込む事によって隠され、消されていく。音色のバリエーション、楽器の音域、間、音の強弱によって、音楽全体が彩られている。
■曲解説
1. George Dreyfus : Sextet for Didjeridu
and Wind Instruments
「ディジュリドゥと管楽器のための六重奏」と銘打たれたこの曲は、現代音楽的な内容で、クラッシックをベースにフリージャズ的な要素も感じる。リズムや和音といった事をあまり重要視せずに、逆に音の響きやそれぞれの楽器の共鳴と干渉といった事が意識されているようだ。
長く同じ音を出し続ける管楽器の中を、管楽器がソロもしくは数名でのからみを回すというのを基本構造にしている。ディジュリドゥはその中を自由に自分のペースで演奏している。
中盤ではディジュリドゥがソロ的な役割を果たしながら、ディジュリドゥのリズムを装飾するかのように賑やかに跳ね回るように管楽器がダイナミズムの波を作っている。西部アーネム・ランドのディジュリドゥの演奏スタイルでありながら、コールを多用し、トゥーツも効果的に時々使っている事に驚かされる。
ディジュリドゥ奏者「George Winunguj」は北部中央アーネム・ランドのコミュニティManingridaの対岸にあるGoulburn島のMaung(Mawng)と呼ばれる人々の出身。60年代のGoulburn島と言えば、Lazarus Lamilamiが著名だが、このGeorgeも同時代をLazarusと共にかけぬけた著名人らしい。
伝統的なディジュリドゥの演奏だけを聞きたい人には、管楽器がガチャガチャうるさくてかなり物足りなく感じるが、ほんの一瞬おとずれるディジュリドゥのみのパートでは倍音豊かで、空気をもらすことなくしっかりと唇で受け止めていることがわかるハッとするほどクールな演奏を聞くことができます。
|